【山 域】八ヶ岳・赤岳・真教寺尾根から県界尾根
【日 付】2014年 5月18日
【時 間】05:00 登山道入口(舗装道路終了部) 05:10 大門川の真教寺尾根入口
06:05 スキー場最上部 ~ 06:15 07:40 牛首山
08:20 2316m標高点 08:45 6/10ポイント
10:35 8/10ポイント 11:00 9/10ポイント
11:10 稜線=10/10ポイント 11:35 赤岳山頂
11:40 小屋=下降ポイント 12:50 展望荘への分岐点
13:20 鉄梯子&鎖場 14:00 大天狗 ~ 14:20
15:45 小天狗 ~ 15:55 16:35 Uターン地点(1860m付近)
17:40 野辺山・清里の分岐点 18:10 大門川の県界尾根入口 ~ 18:15
18:40 登山道入口(舗装道路終了部)
【メンバー】単独行
(地図や写真をクリックすると大きいのが別ウィンドウで表示されます。でもIEは?)
(地図はhtcスマホの 山旅ロガー のGPSログです。)
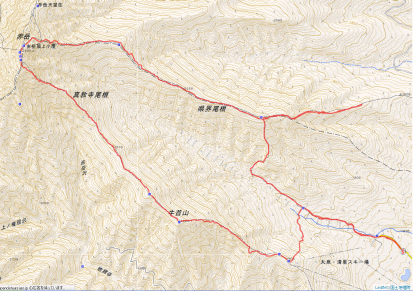
ルート(地図をクリックで拡大表示します)
穂高の奥又白池方面に入ってみたいが、松高ルンゼ出合の100m以上手前から雪が残っている。
まだ行くには早そうなので、交通費的に優しい八ヶ岳へ行くことにした。
昨年の冬だったと思うが、月刊誌・山と渓谷に「かかってこいや真教寺尾根」という記事があった。
そんなにスゴイ尾根なんだろうか?気になっていた。
しかも、隣の県界尾根はもっと難しい様に出ていた。
だったら残雪期も終わりに近いこの時期、真教寺尾根を登って県界尾根を降りてこようと行ってきた。

サンメドウズ清里スキー場駐車場からみる赤岳
残雪は谷筋だけ?
真教寺尾根の樹林帯には雪があるようには見えるけど・・・
いつものように前夜に現地に入り、車泊。
今日は早い目に家を出たので夕方にはスキー場の駐車場に到着した。
登る真教寺尾根と下る県界尾根がよく見える。
なんか雪無さそう?などと見ていたら、夜は駐車場閉めるヨと言われて、100m程下の美し森の展望台のオープンな駐車場へと移った。

大門川沿いの1670mの登山道入口
車は、距離で300m程下に停めた
翌朝は、大門川沿いの1670mの登山道入口近くまで車をあげて駐車し、登り始めた。
足は、買ったばかりのローカットシューズ。ハイカットシューズや他の雪の道具は全部ザックに入れて歩く。
ただ昼間は27℃だったのが今は2℃しかない。
無茶苦茶寒く感じるので、薄手のダウンと古いレインウェアは着ていく。
勿論、歩き始めて身体が寒さに慣れ始めると順番に脱いでいく。

真教寺尾根への道標
おっ、出てきた真教寺尾根への道標

真教寺尾根への道標
まだ新しく綺麗
これなら径も整備されていよう

スキー場最上部に出てきた
このヒュッテ、冬専用でもなさそう
道標に沿って大門川を右岸に戻り、登り始めるとすぐに径は二手に分かれる。
右へ谷沿いに登る踏み跡と左へ尾根に向かう踏み跡。
尾根に出たいのだからと左をとる。
その後も2回程右への踏み跡をやり過ごすと、樹林の伐採地帯で倒木がひどい。
かくして径をロストしても、どうせすぐそこが尾根の上でしょうと獣道を登っていった。
この辺り、獣道と言うより鹿の糞がおびただしく、まるで鹿のトイレだ。
登り切った所はスキー場の最上部の展望ヒュッテだった。
野辺山や清里の見晴らしのいいベランダでちょっと休憩させてもらう。

賽の河原から見る甲斐駒と仙丈ヶ岳
2週間前はあの仙丈の頂に登った
どうしてあれが南アの女王なのだろうネ?

賽の河原から見る赤岳
正面が真教寺尾根、右が県界尾根
雪少ないな~

賽の河原から大門川への下降コース入口
大門川から径を間違わなければここに来るらしい
展望ヒュッテから「3分」という賽の河原にくる。
なるほど南アなど景色がいい。
この一年は、あちらの南アからこの八ヶ岳を見ていた。
オッ、大門沢への道標があった。
道を間違わなければここに上がってこれるらしい。

2120m付近から見る南ア北部の山々
右から、仙丈ヶ岳、甲斐駒、アサヨ峰、北岳、間ノ岳

2120m付近から見る富士山

牛首山
陽の当たる所は雪は消えているが、
樹林の影ではまだ1mぐらいの深さで雪が残っている
やっぱり夏径は歩きやすい。
2120m付近のガレ場の上端から富士山や南アが綺麗に見える。
真教寺尾根は景色がいいが、下降に使った県境尾根からは南アも権現などの山々は見えなかった。
この少し先でいきなり積み上げたように残る雪でローカットシューズでは手が出せず、ハイカットシューズに履き替えた。
勿論、ロングスパッツも履いた。
これで雪の準備は完了。でも、アイゼンもピッケルも要らない。
雪の上には、昨日ピストンされた人の足跡が残っている。

南隣の天狗尾根
2300mコルから見る

天狗尾根
40年程前の年末に一人でラッセルした
それが初めての八ヶ岳だった

8/10ポイント
ここまでは雪は残っていた
2600m付近で傾斜のきつい雪の斜面になったのでピッケルを取り出した。
雪はボソボソなのでアイゼンは着けていない。
8/10ポイントまではそこそこ雪はあるがそれより上は、乾いた岩場になった

当たり良く岩は乾いている
8/10ポイントより上は、陽当たりが良く、乾いた岩を快適に登って権現から来る稜線の径に出た。

稜線直下

稜線、権現からの道と合流
ここが10/10ポイントだった

あれが赤岳の頂上らしい

着いた~赤岳山頂
この標識は、赤岳か?青岳か?

権現と遠くは南ア

山頂小屋
本当に山頂にあるんだここの小屋は

県界尾根へは小屋の北側から

展望荘を見る
ワーッ、北斜面だから雪多い

県界尾根を俯瞰する
県界尾根へは、山頂小屋の北側から下降する。
最初は雪ばかりではなく、時折、ザレ場にも出るのでアイゼン着けずに後ろ向きで下っていく。
そのうちザレ場も見えなくなったのでアイゼンを着けた。
ヘルメットもかぶった。
厄介なのは、トレースがない。
だから径が分からない。
雰囲気これかな?と思わしき所を勘を頼りに下っていく。

トラバース気味に下降してきた雪面を振り返る
夏場はきっと鎖場なんでしょうね
結構きつい傾斜の雪面です
右方向へのトラーバス気味の下降。結構イヤらしい。
滑ったら終わりって感じの斜面なのでピッケルのシャフトを根本まで突き刺しながら一歩一歩下っていく。
そのピッケルを右手で握るので体勢は崩れて、足を確実に蹴り込めない。
蹴り込める体勢になろうとするとピッケル滑落停止の体勢で両手で持つしかない。
ここで滑ると滑落停止をしても、この傾斜とボソボソ雪では止まらないと思う。
だから体勢悪くてもピッケルを確実に突き刺すしかない。
こんな所を下るのだったらもう一本ショートピッケルを持ってくれば良かった。そうすれば、後ろ向きに下れたのに・・・
と思っていたら、ズルッと足場が崩れて突き刺しているピッケルにぶら下がる。
コワイ。

展望荘への分岐点
たったの150m~160m下るのに1時間以上かかってる
それでも慎重に下るしかない

展望荘へのルート
でも今は雪でどこが道だか分からない

壁にホールドを求めながら下降してきた
これしかし、下降は厄介だけど登りなら楽勝では?とも思う。
この時期に歩くのなら、県界尾根を登って真教寺尾根を下る方が楽そう。
ただこの県界尾根、南アとかの景色は見られないのでつまらないと言えばつまらない・・・

2610m付近 鉄梯子と鎖場
もう疲れたのでここの鎖は使わさせてもらった
この先も県界尾根は雪がベッタリ
しかし、急な北斜面からは解放される
急な北斜面を終わって、まっすぐ東へ走る県界尾根になんとか出てきた。
慎重に下ってきたのでかなり精神的に疲れた。
この最後の鎖場の鎖は利用させてもらった。
今日はここまで鎖には指一本触れていない。
その鎖を使って降りている時にサングラスがはずれてカラカラと落ちていった。
すぐに止まるかと思っていたら、最後は雪の上をスーッと消えていった。
この先からは、ベッタリ雪は付いているが傾斜は落ちてピッケルを使わなくても歩いて降りれるようになる。
ただ傾斜が落ち樹林も出始めると見通しが悪くなり、どこが夏径か分かりづらい。
何回かコースアウトしてそれを修正する、という下り方になる。

大天狗
今日、ここまで登って来た人の足跡がうっすら残っていた
緊張から解放されてここでゆっくり休憩する
アイゼンはここで脱いだ
大天狗の2~30m手前で人の足跡が出てきた。
今朝、駐車した所から私より先に出発した人がここまで来て引き返されたようだ。
これで踏み跡が残っていれば安心だと、大天狗で大休止をし、アイゼンを脱いだ。

陽が西に傾いた、赤岳を振り返る
サヨウナラ赤岳。楽しかったよ
陽が西に傾き始めた、赤岳を振り返る。
それにしても、真教寺も県界もやっぱり雪のある尾根には見えないな~。

小天狗
野辺山・清里の分岐のすぐ上
ロングスパッツを脱ぐ
大天狗から先は樹林が濃くなり、陽が差し込まないので雪は融けないのか雪面が堅い。
雪が堅いと潜らないのでありがたいが、踏み跡もまるで残っていない。
結局、夏径はどこ?と足跡かテープかリボンを捜しながらの歩行が続く。
径捜しは気が滅入る。
標識には50分と書かれていた小天狗に1時間半程かかって降りてきた。
すぐ先にあるであろう分岐から南の斜面を駆け下れば大門川に降りる、もうロングスパッツも要らないだろうとはずした。

野辺山・清里の分岐
さあ ラスト ワンピッチ 大門川(清里)へ降りましょう
ほんのすぐ先に分岐はあった。
そして右が清里(大門川)と確認して下っていく。
ピンクのテープも数が増えたようだ。
雪も緩んで足跡もかなりはっきり残っている。
さあもう少しで大門川、と下っていく。

小ピーク
雪が消えるとかなりきつい下りになる。
ここを冬にラッセルすると胸まで潜ってのラッセルになるな~とか思いながら急下降をすると小さなピークが出てきた。
ヘーェ、沢に降りる斜面にピークがあるのか、小尾根に出たのかな?

スキー場の駐車場は結構遠い
見晴らしのいい所に出てスキー場の駐車場が意外と遠くに見えて、結構先は長いな~、とか感じながら下っていった。

野辺山の平坦地
白いのは雪ではありません
ビニールハウスです
よく見ると野辺山宇宙電波観測所が見える
緩い傾斜の背丈の低い笹原を下っていてフト思った。
「どうして沢に下るのにこんな気持ちの良い斜面があるのだ?ここはどこ?」
スマホのGPSを見てみた。
ガーン、全然違う径だ。
このまままっすぐ降りたら?ワーッ車の所に戻れそうにない!
分岐から一体どれぐらい降りてきたの?と等高線を数える。
300m。ウーッ。
今4時半。
300mの登り返しなら1時間と見て分岐に戻れるのが5時半頃になる。
まだ明るい。大門川への径は探せる。
登り返そう。
どうしてもっと早くGPSで確認しなかったのだろう?
それは、分岐で清里への矢印通りの径へ入ったと信じ切っていたからだ。
つらいが、足下だけを見て黙々と登り返す。
変だな~と思った小ピークを越え、冬なら胸までのラッセルなんて想像していた急坂を登って行った。
雪が出てきた。
どこで間違えたのか自分の降りてきた足跡を追う。
とうとう分岐まで戻ってきた。
分岐の標識の写真には雪は写っていないが、2~3m離れると雪で夏径が出ていない。
どうして間違えたの?

大門川沿いの県界尾根入口
フーッ、やっと降りてきた
確かに、元々、清里への径に進んで行っている。
雪の上を数メートル進む。
雪で径は分からない。
雪が堅いので踏み跡も残っていない。
立ち止まってキョロキョロする。
左手下の方に、ピンクテープ発見。
よし夏径はあれだ、とそっちへ向かう。と、それは清里ではなく野辺山へ降りる径だ。
なんと分岐の標識から10mも進まずに径を間違えていた。
雪の上で立ち止まってキョロキョロせずに、もうあと数メートルも進めば、残雪が薄くなって夏径がうっすら出始めていた。
さらに10mも行けば、南面の急傾斜が始まって雪は完全に消え、夏径が大門川へと下っていた。
朝は、登り始めて左へ進んで径を失い、下りも左に径を見付けて違う尾根を下ってしまった。
大門川、もうキライ。
【 終わってみれば楽しい八ヶ岳 】
八ヶ岳、もし悪い言葉で表現すれば、 「北アや南アの様なスケールがない」 同じことをいい言葉で表現すると、 「北アや南アの面白さがこぢんまりとうまくまとまっていて楽しい」となる。 今回は、最後に径間違いで辛い思いをしたが、全体的には楽しい山だった。 八ヶ岳。 それは、まだまだ山頂は遠いな~と思って登っているとフッと近くに山頂が現れる。 それがいつも八ヶ岳で感じる私の印象だ。 今回、山頂から下降の県界尾根にトレースがなかった。 だから夏径がどこか分からなかった。 その苦労した分が楽しさを増幅したのかも知れない。 連休時に人のトレースを追っかけたのでは、確かに早く歩けるかも知れないが面白くはない。 久々の八ヶ岳、やっぱり良い山でした。